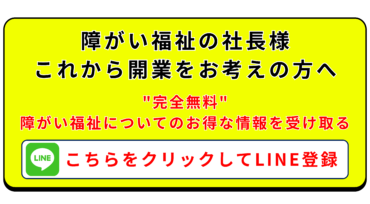「就労選択支援」は 2025年10月(令和7年)に始まる新しい障害福祉サービスです。目的は、就労を希望する障がいのある人に対して、本人の強みや課題を本人と協同して整理し、本人が就労先等進路を選び、自分の働き方について考え決めていくことをサポートすることです。利用者は見学や短期体験を通じて複数の選択肢を比較し、ミスマッチを防ぎながら進路を決定します。
法律改正で示された「選択支援」の必然性
2022年12月に成立した改正障害者総合支援法では、「多様な就労ニーズへの対応」が明文化されました。ここで新設されたのが就労アセスメントを活用する「就労選択支援」です。短期間で適性を可視化し、本人がA型・B型・移行支援などを比較検討できる仕組みとして位置づけられています。制度の施行日は2025年10月1日です。
現場課題:雇用数は増えても“ミスマッチ離職”が多い
障害者の民間雇用者数は**64万2,178人(2023年6月時点)**で過去最高を更新。それでも『障害者雇用率』達成企業は約5割にとどまります。
『障害者雇用率』は2024年に2.5%、2026年に2.7%へ段階的引き上げが予定され、人手不足の解消策として質の高い定着支援が求められています。
これらの数字が示すのは「雇用の受け皿は増えたが、本人の適性や意向と職場・サービスの選択が噛み合っておらず、適切なサービス等につなげられていない」
という現実です。
就労選択支援は、このギャップを最前線で埋める“入口サービス”として創設されました。
いつ・どう始まる?開始時期と段階的スケジュール
就労選択支援の利用開始時期は、現在下記のように予定されています。
- 就労継続支援B型を新規に利用検討している人(50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者を除く)は、原則として2025年10月からサービス開始。
- 就労継続支援A型を新規に利用検討している方および就労移行支援を2年間を超えて利用を希望している人は、原則として2027年4月から開始。
- 特別支援学校等の在学者も就労選択支援の利用が可能となります。
対象となる人と利用要件
対象者
- 就労移行支援又は就労継続支援を利用したい人
- 現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している人
義務化フェーズ別の“必須”グループ
| 施行段階 | 義務化される利用者 | 例外・免除 |
| 第1段階
2025年10月1日〜 |
新たに就労継続支援B型を利用したい人 | (1) 50歳以上 (2) 障害基礎年金1級受給者 (3) 一般就労経験があり高齢・体力低下で就労困難な人 |
| 第2段階
2027年4月1日〜 |
新たに就労継続支援A型を利用する人/就労移行支援を標準期間(2年)超えて継続利用する人 | ― |
下記の場合、従来の就労移行支援事業所等によるアセスメントで代替可能。
・近隣に就労選択支援事業所がない場合
・就労選択支援事業所数が少なく、待機期間が生じる場合
任意利用できるケース
- 新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用を希望する人(2026年度まで)
- 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新を希望する人
- 就労経験がある者(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。)、50 歳に達している者、障害基礎年金1級受給者のいずれかであって、新たに就労継続支援 B 型を利用を希望する
提供されるサポート内容
- 作業場面等を活用した状況把握
- 本人との面談による就労に関する希望・ニーズの把握
- 家族や関係者との面談による情報収集
- 模擬的就労場面の設定や職場実習により本人の希望を把握
- 標準化検査、職務分析、ワークサンプルによる本人の特性を把握
- 多機関連携によるケース会議
- 本人や家族、関係機関とアセスメントの結果を共有し、本人の主体的な選択を支援するための会議
- アセスメントシートの作成
- 本人が希望する就労支援を検討するために活用するために、1. の情報をアセスメントシートに落とし込み、就労に向けた今後のプランを考えていく。
- 事業者等との連絡調整
- 1.〜3. の結果を踏まえ、必要な関係機関との連絡調整を行う
本人と協同して1.〜4. を行い、随時、本人への情報提供等を行います。
既存の就労系サービスとの違い
| ポイント | 就労選択支援 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 主な目的 | 最適な支援サービスを“選ぶ” | 一般就労へ移行 | 雇用型の継続就労 | 非雇用型の継続就労 |
| 期間 | 3か月程度(短期) | 2年まで | 制限なし | 制限なし |
| 雇用契約 | なし | なし | あり | なし |
本制度は「働く訓練」ではなく**“選択のための準備”**に特化している点が最大の違いです。
利用までの流れ
- 利用希望・情報収集
- 本人:市区町村へ「サービスを利用したい」と相談する
- 市区町村:就労選択支援を利用するため、計画相談支援事業所に「サービス等利用計画案」の作成を依頼する
- 計画相談支援事業所:本人と就労選択支援事業所を交えて面談を行い、支援内容を調整する
- 就労選択支援事業所:事業所の見学やサービス説明を行い、本人の意思を確認する
- 計画案作成
- 計画相談支援事業所:ヒアリング内容を基に「サービス等利用計画案」を作成し、市区町村へ提出する
- 支給決定・契約
- 市区町村:計画案を審査し、サービス給付の可否を決定する
- 計画相談支援事業所:支給決定後、「サービス等利用計画」を交付し、サービス担当者会議を開催する
- 就労選択支援事業所:本人と利用契約を締結する
- 多機関連携
- 既存の関係機関はサービス担当者会議に参加する
多機能事業所として運営できる?
就労選択支援を新設する際、「すでに就労移行支援やA 型・B 型を運営している事業所と同じ拠点で実施できるのか」「スタッフや設備をどこまで共用できるのか」といった“多機能化”の疑問が必ず浮上します。次の表では、併設の可否・兼務要件・同日利用の算定ルールなど、運営側が押さえておくべき論点を一覧で整理しました。
| 論点 | どう定められているか |
| ① 併設そのものは可能か | 就労移行支援・A型・B型などと同一施設内で就労選択支援を実施してよい。いわゆる「多機能型」の枠組みに該当し、人員・設備基準をそれぞれ満たせば指定取得ができる。 |
| ② 支援員の兼務 | 既存の就労移行・A型・B型の職業指導員等が就労選択支援員を兼務してよい。勤務時間は常勤換算で算入可。要件は「就労選択支援員養成研修」の修了(経過措置あり)。厚生労働省 |
| ③ 同一法人・同一利用者の利用制限 | 客観性確保のため、利用者が現在通っているA型・B型・移行支援と同一法人が運営する就労選択支援は原則利用不可。ただし「地域に他事業所がない」「通所が困難」などやむを得ない場合は例外的に認められる。厚生労働省 |
| ④ 同一日の併給ルール | – 放課後等デイ・障害児入所施設とは同日併給可(支援内容が重複しないため)。
– 生活介護・移行支援・A型・B型など日中活動サービスとは同日二重算定不可。時間帯を分ける場合は報酬按分で対応。厚生労働省 |
| ⑤ 会計・記録の分離 | 多機能型でもサービスごとに利用記録・請求コードが異なる。指導監査では重複請求・帳簿区分が重点確認項目。 |
まとめ――多機能事業所として運営するポイント
- 移行支援・A型・B型と同一拠点で開設できるが、人員・設備基準はサービスごとに個別充足が必要
- 支援員を兼務 現行スタッフを「就労選択支援員」として活用
- 同一法人利用制限 利用者が在籍する事業所と同法人の場合は原則不可だが、事業所不足や通所困難などの例外規定を把握しておく
就労選択支援の申請書類作成や事業所選定のアドバイス、関連手続きまでトータルにサポートします。お気軽にお問い合わせください。
参考文献